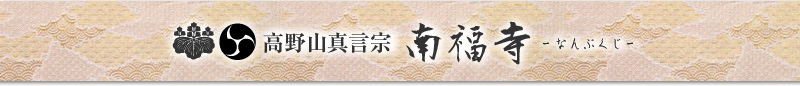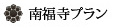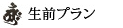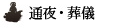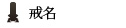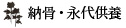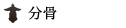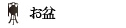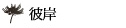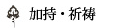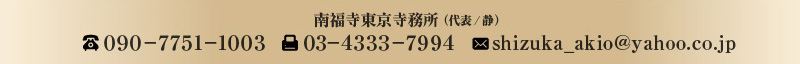●初七日
命日も含めて七日目に行うのが初七日です。
初七日は骨上げから二~三日後となります。遠方の親戚に葬儀後再び集まっていただくのは大変なので、葬儀の日に合わせて行うことが多くなっています。
●四十九日までの遺族の心得
葬儀のあと、遺骨、遺影、白木の位牌を安置し、花や灯明、香炉を置くための中陰壇(後飾り壇)を設けます。中陰の四十九日間、家族は故人が六道を乗り越え極楽浄土に行けるように供養します。七日ごとの法要が無理な場合でも、お線香をあげ手を合わせてお祀りしたいものです。特に三十五日は、重要な裁きの日とされるので、丁寧に拝むと善しとされています。
一般には四十九日までが「忌中(きちゅう)」で、この期間は結婚式などのお祝いごとへの出席や、神社・神棚への参拝は控えるようにします。
●位牌の準備
白木の位牌は、葬儀の野辺送りに用いる仮の位牌です。四十九日法要までは、遺骨、遺影と一緒に中陰壇に祀りますが、四十九日までには漆塗りの本位牌を作ります。戒名の文字入れに2週間位かかるので、早めに仏壇店に依頼しておくとよいでしょう。
四十九日法要を終えた後、本位牌は仏壇に安置しますので、仏壇のない家は併せて手配します。
白木の位牌は、四十九日法要の時に菩提寺に納め、新しく作った本位牌に住職から「開眼(魂入れ)」をしていただきます。お寺で四十九日法要を営むときは、本位牌を持参して開眼をお願いし、帰宅後、仏壇に安置します。
●四十九日忌
四十九日は、来世の行き先が決まるもっとも重要な日で、「満中陰(まんちゅういん)」と呼ばれます。
故人の成仏を願い極楽浄土に行けるように、家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。
そして、この日をもって、「忌明け(きあけ)」となるので、法要後、忌明けの会食を開きます。
法要は忌日(きび)の当日に行うのが理想ですが、実際には参列者の都合もあり、最近は週末に行うことが多いようです。
四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活にもどる日でもあります。
●百カ日
百カ日は、亡くなった命日から数えて100日目の法要です。
「卒哭忌(そつこくき)」ともいわれ、泣くことをやめ悲しみに区切りをつける日で、家族や親族などの身内で法要を営みます。