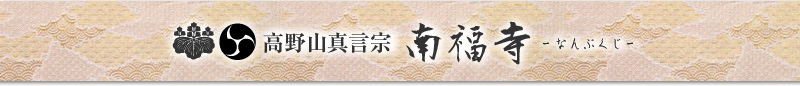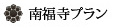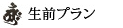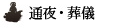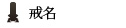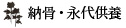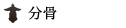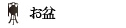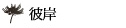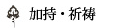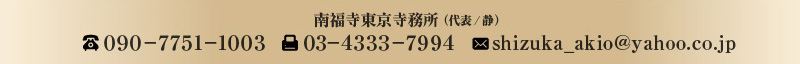●施主の役割
四十九日や一周忌などの法事を行う当主を「施主(せしゅ)」といいます。
一般には葬儀の喪主(もしゅ)を務めた人が施主を務めます。
施主は主催者として、次の準備をします。
・菩提寺の住職と相談して、誰の何回忌の法要かを伝え日時を決める。
・法要の場所や招待する人数を決める。
・法要の後の会食「お斎(とき)」の場所を決め、案内状を送る。
・会食の料理、席順を決める。
・引き出物の用意をする。
・御布施やお供え物の用意をする。
まず、住職と相談をして、法要を営む日を決めます。
卒塔婆を立てる場合は、事前に住職に依頼しておきます。
次に、法要場所を自宅か、菩提寺、あるいは斎場で行うかを決めます。一般に関東は菩提寺または霊園、斎場で、関西は自宅で法要を営むことが多いようです。
日取り、場所が決まったら、招待客を決め、案内状を送り、返事をもらいます。
参列者の人数が確定してから、会食、引き出物を用意します。表書きに「志」か「粗供養」、下に施主の家名を書きます。
同じ年に法要が重なった場合、まとめて行ってもよいとされ、案内状には誰と誰の法要かを明記します。これを「併修」あるいは「合斎」といいます。
●当日
法事の当日は、次のようにすすめるのが一般的です。
1、 住職の読経
2、 参列者による焼香
3、 住職の法話
4、 墓参り、挨拶
5、 会食
焼香の順番は、施主が一番始めにお焼香し、その後、故人と関係の深かった順に行うのが一般的です。
法事の構成を大きく分けると、住職の読経による法要と、その後の会食に分けられます。
このような法要後の会食のことを「お斎(とき)」といい、住職が出席した場合は正客となります。
法要はお寺や自宅、霊園で営まれ、引き続き同じ場所でお斎に移る場合と、料理屋などへ場所を移動してお斎する場合とがあります。
また法要は家族や親族だけで行い、その他の故人と縁の深かった友人や知人は、直接お斎の会場に来ていただく場合もあります。その場合、故人の遺影を飾った献花台に献花をして頂いたりします。
住職や縁の深かった友人から挨拶を頂いたり、「献杯(けんぱい)」の発声がされることもあります。
●法事にかかる費用
法事にかかる費用は、法事の規模によって異なりますが、あらかじめ目安を立てておいたほうがよいでしょう。
・会場費・会食費(お斎の飲食代)
・御布施(住職への謝礼)
・引き出物
・その他(案内状の印刷代、送迎の車代)
●御布施
御布施とは、自分の持てるものをできるだけ他人に施しをすることで、「法施(ほうせ)」、「無畏施(むいせ)」、「財施(ざいせ)」の3種類があります。
法施は仏法を説いて人に施すこと、無畏施は人の心配事や苦労を取り除いてあげること、財施は金銭物品等で施すことで、この財施が現在の御布施になっています。もともとは喜んで仏に差し出すもので、額が決まっているわけではありません。
また、自分の気持ちを尽くして施すわけですから、御布施がその人の社会的地位とか資産に応じて変わるのは当然のことです。実際に、どれくらい包むのか戸惑う場合は、お寺にくわしい檀家や親戚に聞くか、お寺に直接相談するとよいでしょう。
※下記は、あくまで参考にしてください。
御布施
10,000~100,000円のあいだで、自分にふさわしいと考える額で。
表書きは、「御布施」とし、「御経料」とか「御礼」とは書きません。
御車代
住職に自宅や墓地まで出向いてもらった場合、足代として渡します。
5,000~10,000円程度。
御膳料
法要後の会食に住職が欠席したとき、住職に渡します。
5,000~10,000円程度
●塔婆供養料
法要で卒塔婆を立てる場合に包みます。
寺により卒塔婆料は決まっています。
1本1,000~5,000円。